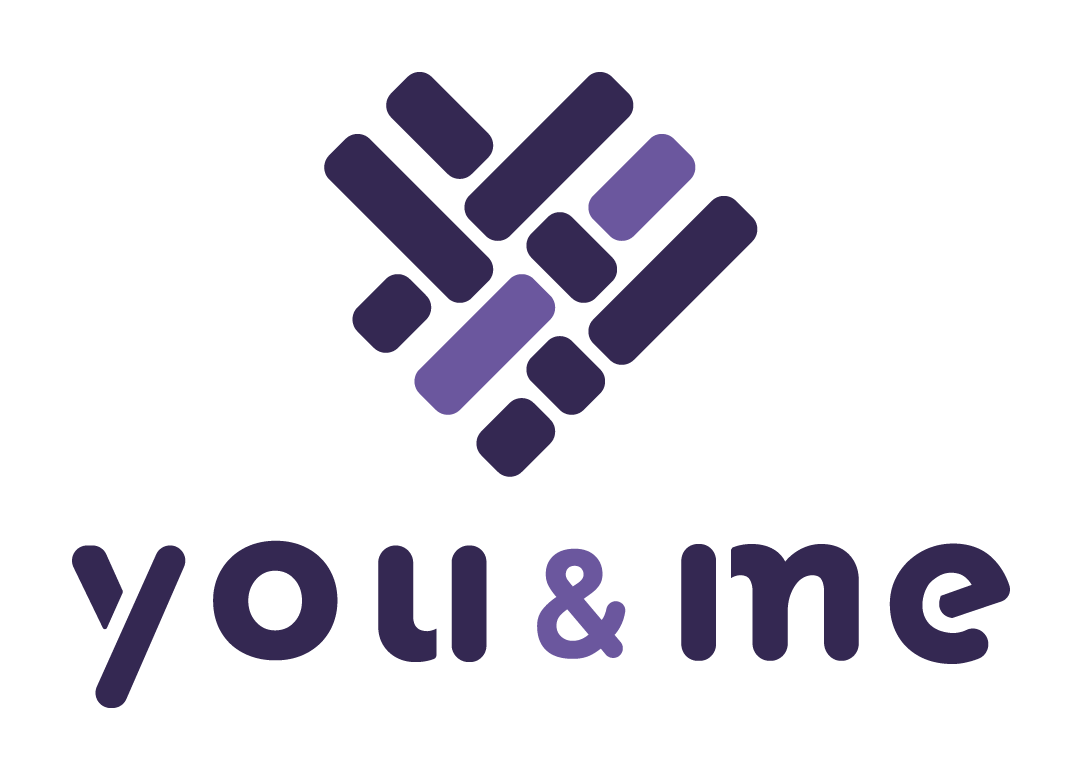2025年07月17日

新卒・中途採用を成功させるうえでは、求人原稿の作成やチャネル・媒体の選定だけではなく、応募を受け付けたあとの工程も重要です。また、全行程を丁寧かつ迅速に対応するためには、人員体制の整備や社内意識の改善も必要になってきます。
この記事では、前編に続いて新卒・中途採用でよくある失敗例を解説します。100社以上の採用支援実績がある弊社ユウミの経験をもとに、採用が成功しやすい会社の特徴もあわせて紹介します。中小企業の人事担当者や採用担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
新卒・中途採用で失敗が多い7つの要素
新卒・中途採用で失敗する場合、以下に挙げる要素のいずれか、あるいは複数でつまづいている傾向があります。
- 1.準備
- 2.求人原稿
- 3.チャネル・媒体
- 4.応募者対応
- 5.アフターフォロー
- 6.人員体制
- 7.マインド
後編では、「4.応募者対応」~「7.マインド」のよくある失敗例を紹介します。
「1.準備」~「3.チャネル・媒体」については前編で解説しているため、あわせてチェックしてみてください。
新卒・中途採用でよくある失敗例【応募者対応編】
新卒・中途採用の応募者対応でよくある失敗例は、以下の2つです。
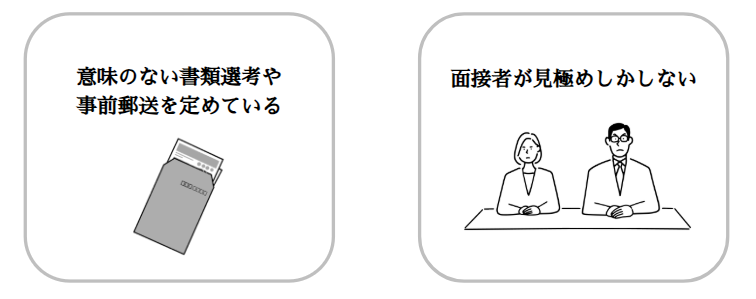
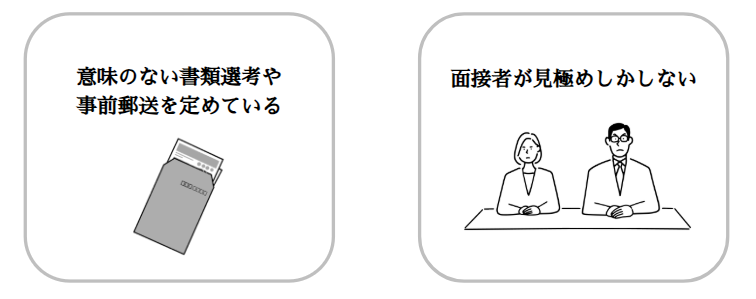
なお、応募者対応の重要性やポイントについて知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
意味のない書類選考や事前郵送を定めている
意味のない書類選考や事前郵送は、求職者の心理的ハードルを高めるばかりで採用失敗につながりやすくなります。「絶対にこの会社の面接を受けたい」という動機付けができていないと、応募は見込めません。
大切なのは、面談や説明会などで「実際に会って話をすること」です。求職者に選んでもらえるような情報を対話の中で伝えられれば、動機付けを促せます。書類選考のあとに面談・説明会を実施している場合は、順番を入れ替えることも検討してみましょう。
面接者が見極めしかしない
面接者が一方的に質問をして、「見極め」だけをするのも採用失敗あるあるです。そもそも、近年の求職者は複数の会社へ求人応募しており、「応募=1番入りたい会社」というわけではありません。 その分、面接では自社の魅力を伝える「惹きつける工夫」が重要です。近年の採用市場は売り手(求職者)優位であり、「求人情報を出す会社側が選ばれるよう努力する時代」になっていることを忘れないようにしましょう。
新卒・中途採用でよくある失敗例【アフターフォロー編】
新卒・中途採用のアフターフォローでよくある失敗例は、以下の3つです。
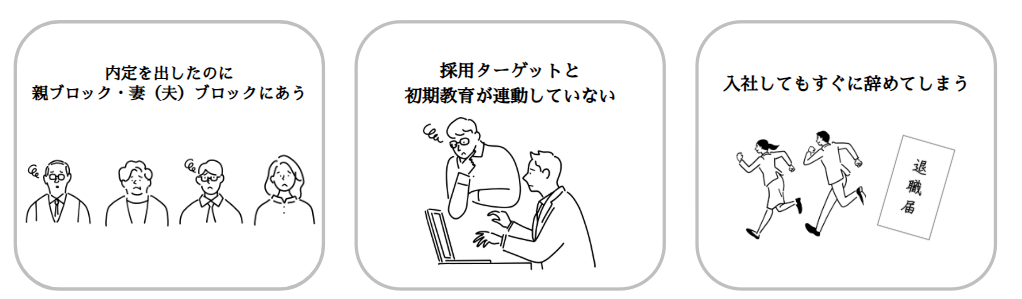
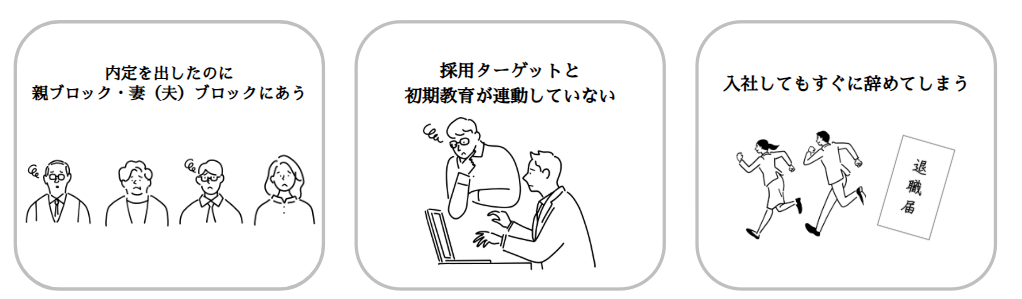
それぞれ詳しく見ていきましょう。
内定を出したのに親ブロックや妻(夫)ブロックにあう
応募者対応までは順調に進んでおり、本人も入社意欲があったにもかかわらず、内定辞退によって採用が失敗するパターンもあります。このような背景にあるのは、以下のような想いを持つ親・妻(夫)に入社を止められたというものです。
- 「勤続年数は長いほど良い」という価値観
- 「転職は嫌」という妻(夫)の気持ち
- ホームページなどが古く、「本当にこの会社へ転職しても大丈夫?」という不安
もちろん、転職を止めるのが本人のためになるケースも少なくありません。しかし、企業側からすると、「優秀な人が来そうだったのに」ともったいなく感じるでしょう。
企業側ができることとして最も有力なのは、3つ目の情報発信に関する改善です。求職者だけではなく、そのご家族にも信頼感・安心感を与えられるよう、自社ホームページや会社説明用パンフレットなどを整えておきましょう。
採用ターゲットと初期教育が連動していない
ターゲットと初期教育が連動していない状態は、新卒・中途採用ともに早期離職の原因になります。
よくある失敗例が、「未経験者OK!一から育てます」と求人原稿に記載していたにもかかわらず、初期教育が不十分あるいは確立されていないというケースです。このような事態を避けるためには、下表のような体制構築や支援が必要になってきます。
| 未経験者を採用した場合 | 経験者や管理職を採用した場合 |
|---|---|
| ・不安を感じやすいところの把握 ・研修制度など教育体制の構築 ・先輩など横のつながりを作る機会の提供 ・日常的にフォローできるような体制の構築 など |
・各部署を見学する機会の提供 ・勉強会の実施 ・懇親会の開催 ・メンター制度の導入 など |
自社とマッチした方が活躍する機会を逃すことのないよう、採用活動とともに教育体制の整備も同時に進めましょう。
入社してもすぐに辞めてしまう
早期離職の原因は前述の教育体制以外にも、以下のようなミスマッチが挙げられます。
- 業務内容や会社の雰囲気が思っていたのと違った
- 働き方が合わない
- 給料が思っていたより低かった など
ミスマッチは求人原稿の内容が実態とかけ離れている、あるいは魅力的な点のみ書いているケースで起きやすくなります。そのため、求人原稿では実情に沿って大変なところも正直に書いたうえで、「それでも、この会社で働きたい」と思ってくれる人材を採用することが大切です。
求人原稿の書き方やポイントについて知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
新卒・中途採用でよくある失敗例【人員体制編】
新卒・中途採用の人員体制でよくある失敗例は、以下の2つです。
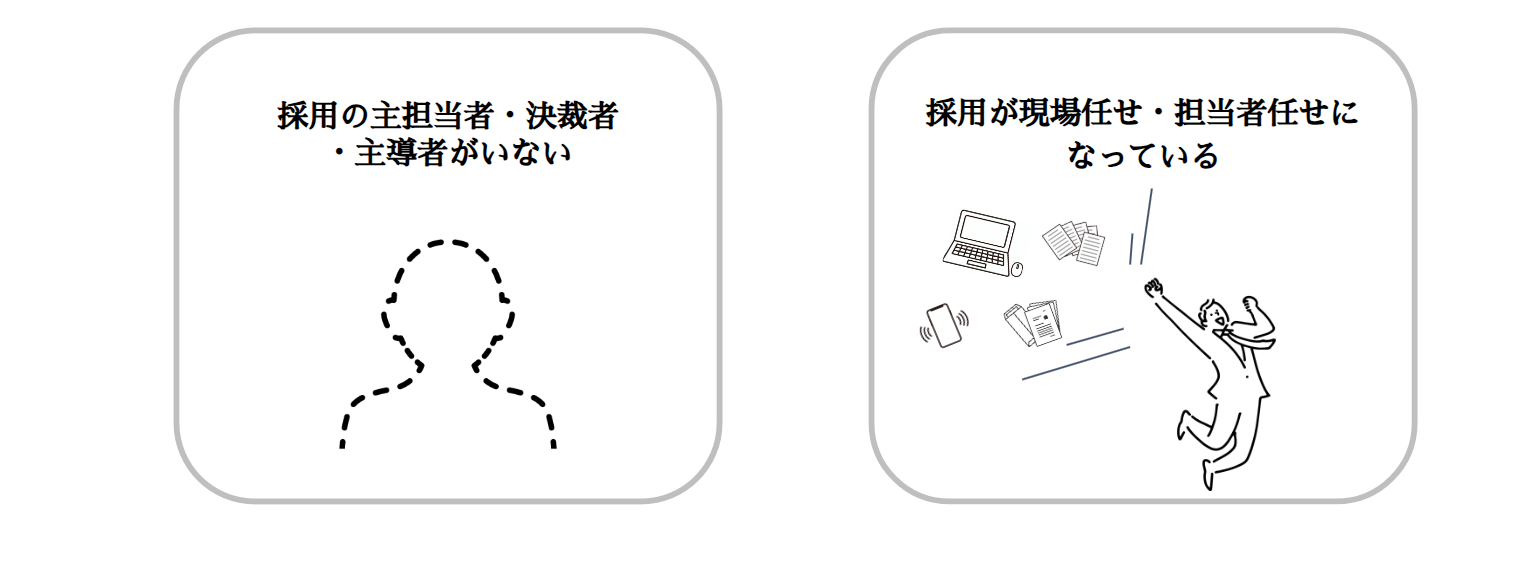
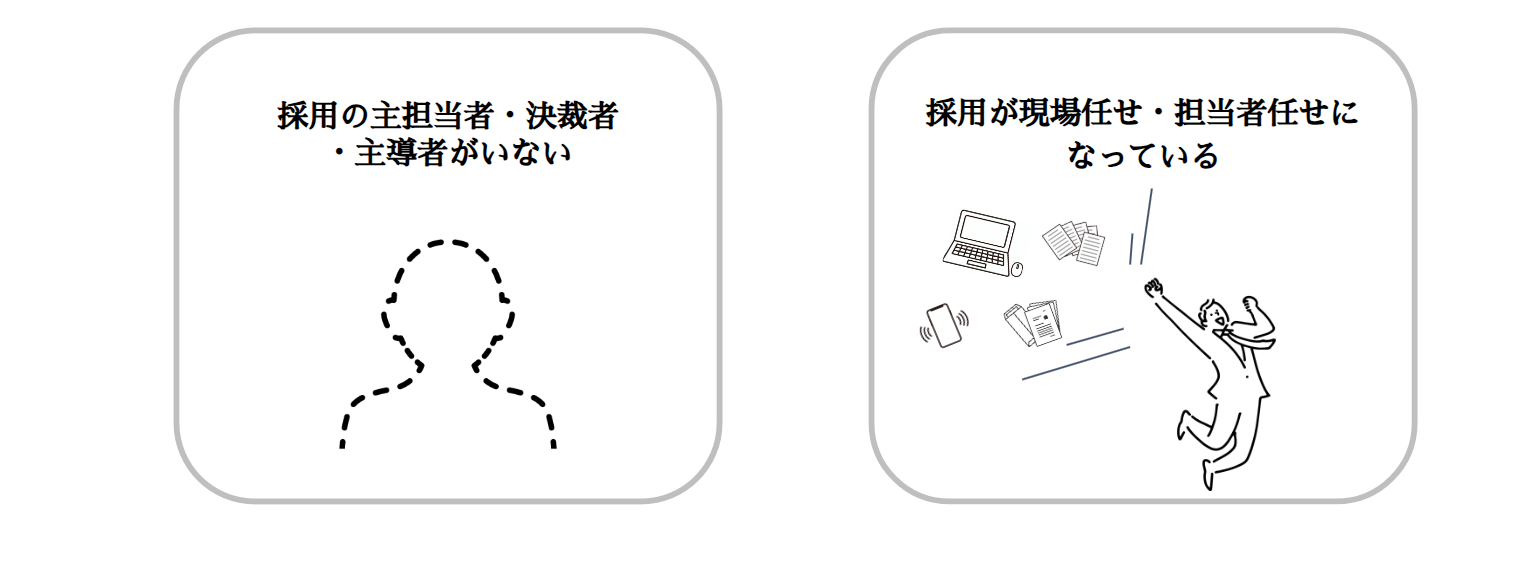
それぞれ詳しく見ていきましょう。
採用の主担当者がいない
専任の担当者・決裁者・主導者がいない状況も、採用が失敗しやすいパターンの1つです。そもそも採用担当者は下表のように、企業規模によって配置状況が変わる傾向にあります。
| 企業規模 | 採用担当者の状況 |
|---|---|
| 従業員数50人未満 | 社長が通常業務のかたわら、採用活動を進める |
| 従業員数50人以上 | 労務や総務の担当者など事務スタッフが兼任する |
| 従業員数100人以上 | 採用担当者を配置する企業が増える |
捻出できる時間が少ないと、採用活動がなかなかスムーズに進まないのは容易に想像できるでしょう。ただし、専任の担当者はいるものの、採用経験があまりないために失敗するケースも多々あります。そのようなときは、外部のプロに採用業務を委託するのも1つの方法です。
なお、弊社ユウミでは人員が少ない企業でも採用活動が成功するよう、戦略立案から実務代行まで一気通貫で支援しております。
自社で長く活躍できる人材を採用したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
採用が現場任せや担当者任せになっている
現場任せ・担当者任せだと採用活動がなかなか進まないだけではなく、求める人材像のズレなどによってミスマッチも起きやすくなります。
採用を成功させるためには現場や人事はもちろん、経営陣も含めて会社が一丸となる必要があります。具体的には自社の経営戦略に沿って、以下のような内容を1つずつすり合わせることが大切です。
- 数年後にどのような組織にしたいのか
- その組織ではどのような方が活躍するのか
- どのような方がよりマッチしやすいか
なお、採用担当者の確保といったリソース面は、採用力の一端を担う「企業力」で唯一コントロールが可能な要素です。
企業力の基礎知識や伸ばし方について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
新卒・中途採用でよくある失敗例【マインド編】
新卒・中途採用でよくある勘違いは、以下の4つです。
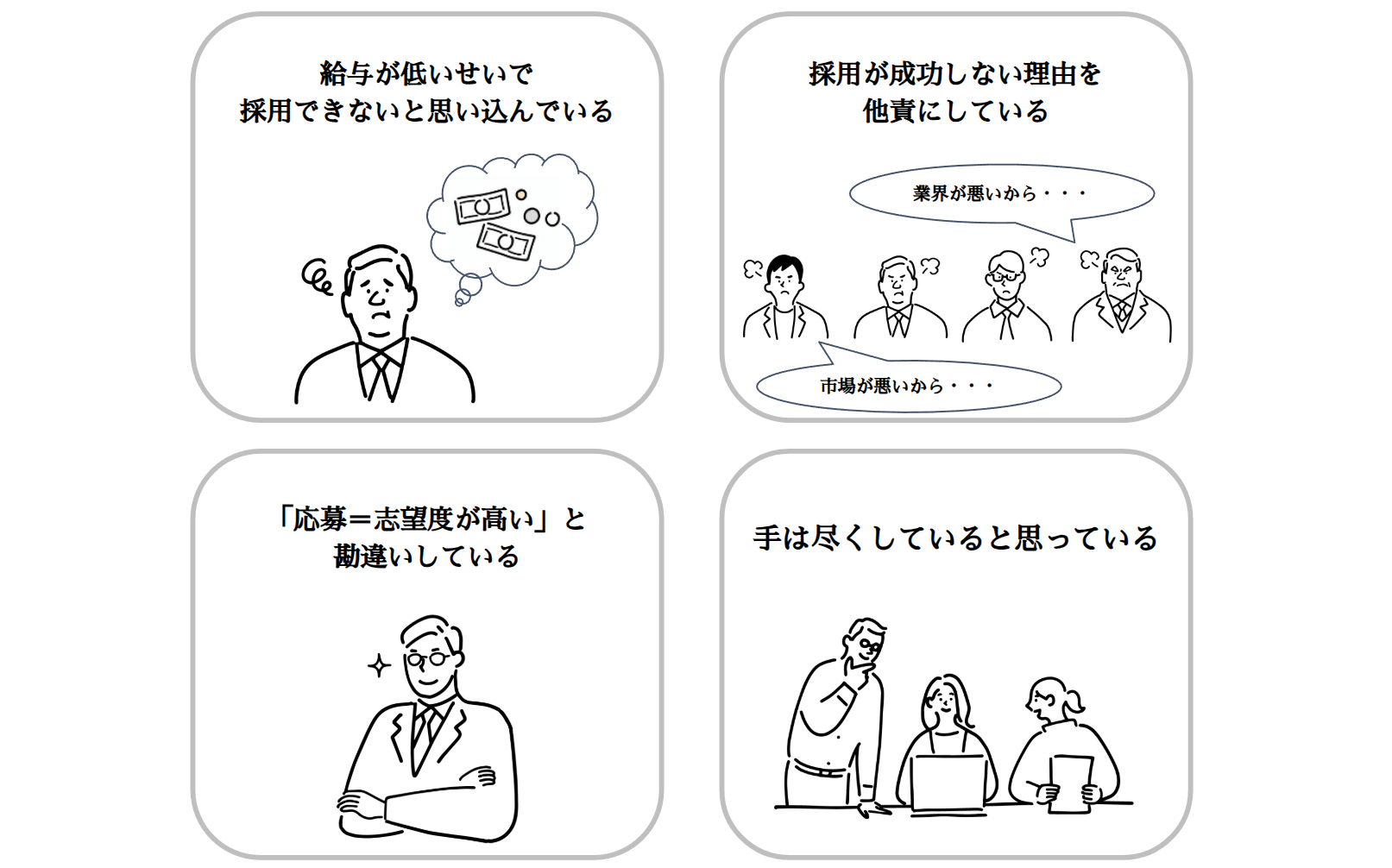
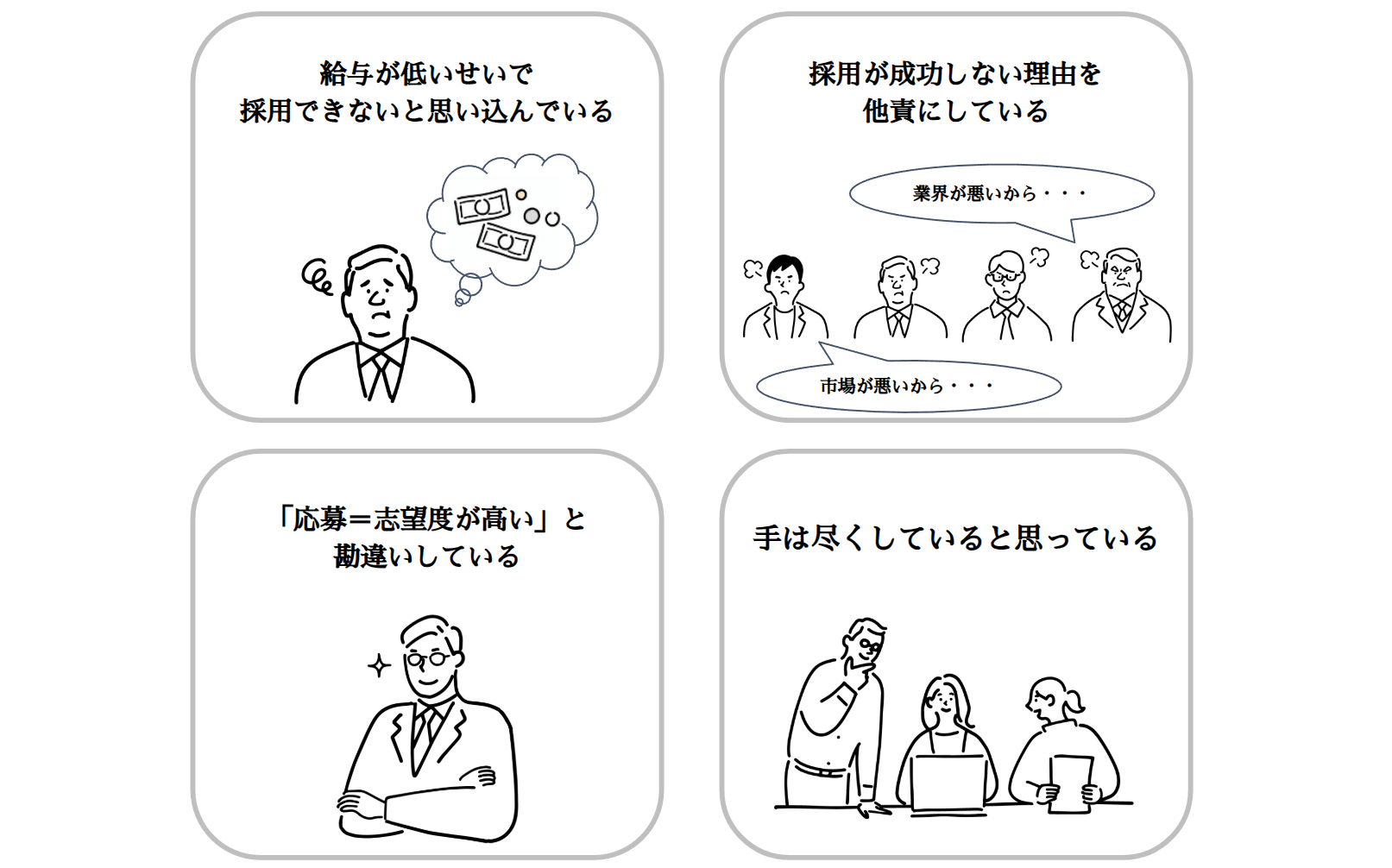
それぞれ詳しく見ていきましょう。
給料が低いせいで採用できないと思い込んでいる
新卒・中途採用がなかなか成功しない会社では、社長が「採用できないのは、給料が低いせいだ」と思いこんでいるケースがあります。しかし、給料の低さは必ずしも採用の成否を左右するものではありません。
たとえ金額を上げても、お金を重視する人しか入社せず、より良い給与条件の会社を見つければ再度転職してしまいます。採用活動を進める際は、給料以外にある自社の魅力や強みを見つけ、求人票へ落とし込んでいくようにしましょう。
自社が持つ魅力の見つけ方について具体的なテクニックを知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
採用が成功しない理由を他責(市場や業界)にしている
採用活動に本腰を入れられない会社の中には、採用失敗の原因を市場や業界など他責にしがちです。しかし、市場や業界の状況が悪くても、同業他社へ転職し活躍している方はたくさんいます。つまり、自分たちの手が届く範囲で改善を進めていくことが大切なのです。
また、社屋の古さを採用失敗の原因として挙げる会社もありますが、求職者全員が外見だけで入社先を選んでいるわけではありません。社屋以外にも目を向け、1つずつ改善を積み重ねていく意識を持ちましょう。
なお、弊社ユウミでは「採用力=企業力×戦略力×改善力」と定義し、特に戦略力と改善力の見直しが採用力を大きく伸ばすと考えています。採用戦略の立て方や、よくある失敗と対処法について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
「応募=志望度が高い」と勘違いしている
「応募=志望度が高い」と勘違いしたまま応募対応にのぞむのも、失敗例の1つです。有効求人倍率が年々上がり、売り手市場となっている近年では「求職者が会社を選ぶ時代」になっています。
このような状況の中で「求職者側から積極的に連絡してくるだろう」「応募者は相当の熱量があるはずだ」と勘違いしていると、あらゆる採用活動が後手に回ってしまいます。「応募=一定の興味を持っている」という認識に改め、自社の魅力訴求など求職者の興味関心を引き上げる努力を怠らないようにしましょう。
手を尽くしていると思っている
「これだけ手を尽くしているのに、なぜか採用できない」というのも、よくある失敗例です。採用活動を支援している側から見ると、実は「言うほどできていない」というケースがほとんどです。
専任の採用担当者がいる、あるいは採用コンサルや採用代行業者を使っている会社であっても同様です。そのような会社でも、「本当にやるべきことが見えてない」「見えていてもやっていない」というケースが少なくありません。
採用活動を経て求める人材の確保・定着を実現し、かつ再現性があると自信を持って言えない場合は、初心に帰って社内状況の把握から見直しましょう。
【失敗から学ぶ】採用が成功しやすい会社の特徴
応募者対応〜マインドでの失敗例を踏まえると、採用が成功しやすい会社の主な特徴としては以下の5つが挙げられます。
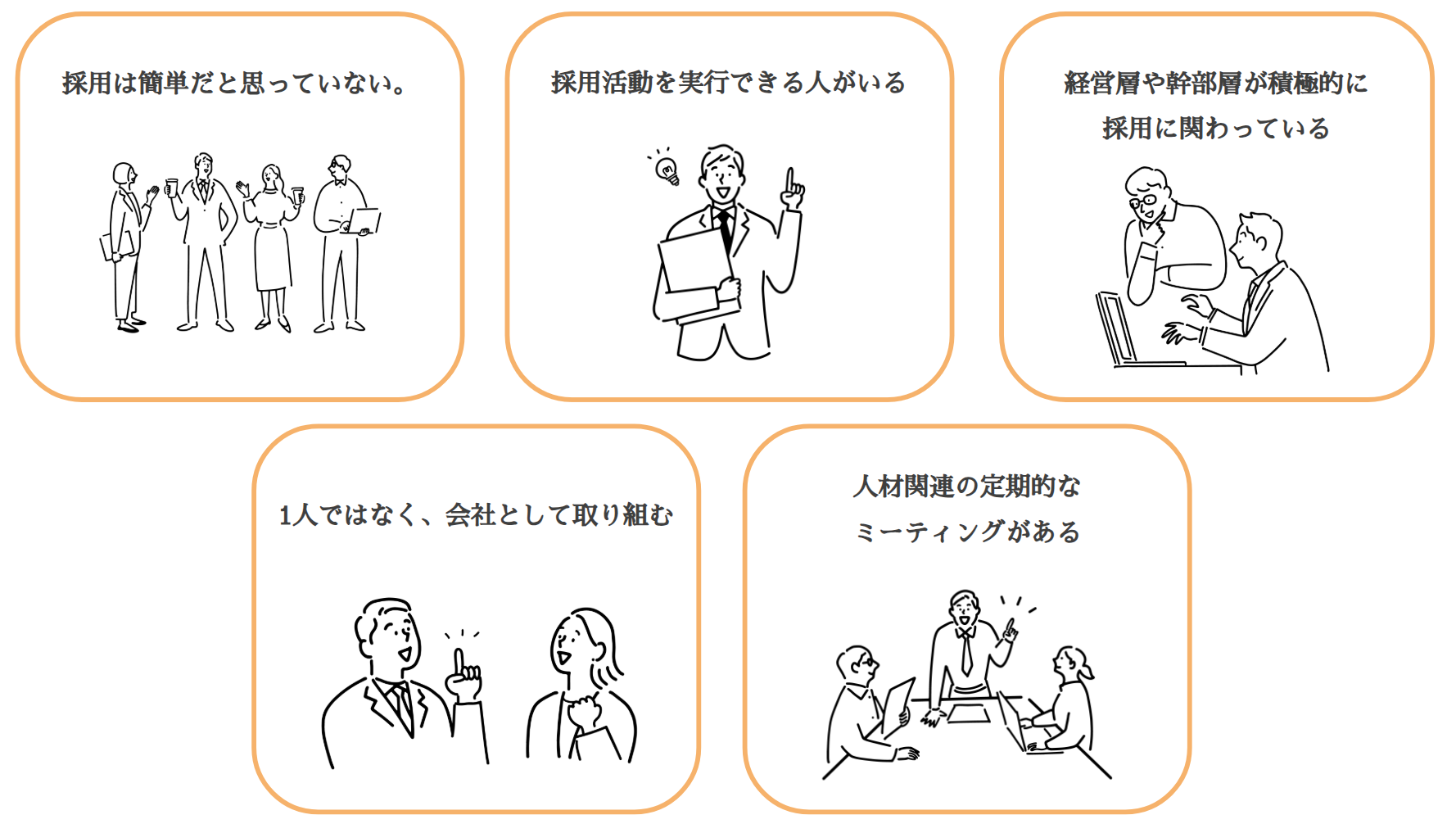
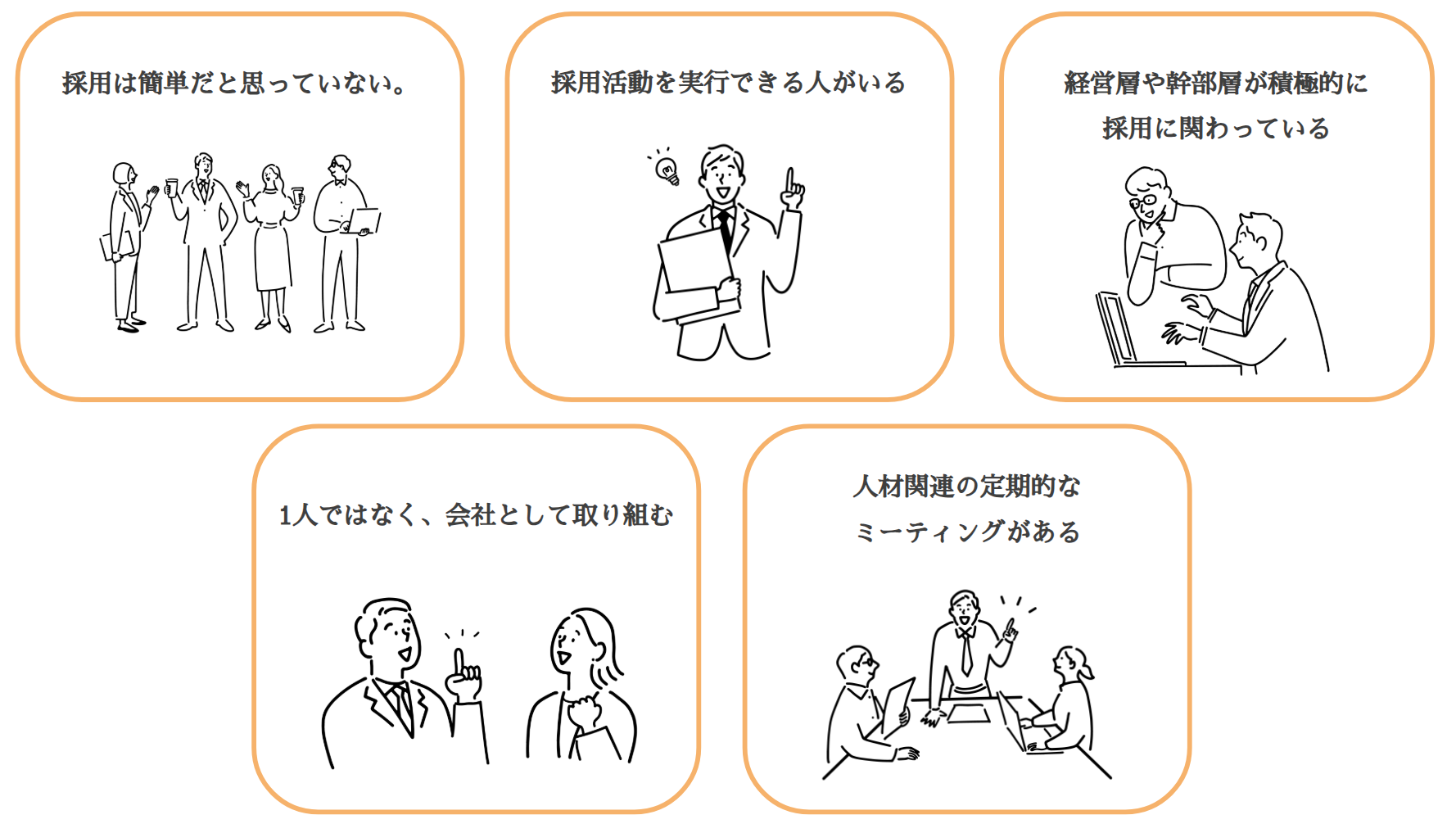
ただし、社内リソースが不足していて自社だけでは対応が難しい場合などは、必要に応じて外部の専門会社へ相談することも大切です。採用が成功する会社の共通点について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
採用失敗から抜け出すために見直すべき点は多岐にわたる
採用活動における本質的なゴールは、入社した人が自社で活躍し続けられることにあります。つまり、採用を成功させるためには、人材の「定着」まで見越したフォロー体制の整備や社内意識の改善が必要です。
弊社ユウミでは「採用力=企業力×戦略力×改善力」という定義のもと、戦略立案から実務代行まで一気通貫で支援しております。過去3年で100社をサポートし、顧客満足度・採用成功率ともに97%以上です。再現性のある採用方法で継続的に人材の確保・定着を図りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。